著者の菊田さんより頂きました「原論文から解き明かす生成AI」を読んだので簡単な紹介を書きます。本日8月18日発売です。私の好みにぶっ刺さり、最近読んだ書籍のなかでダントツで良かったです。
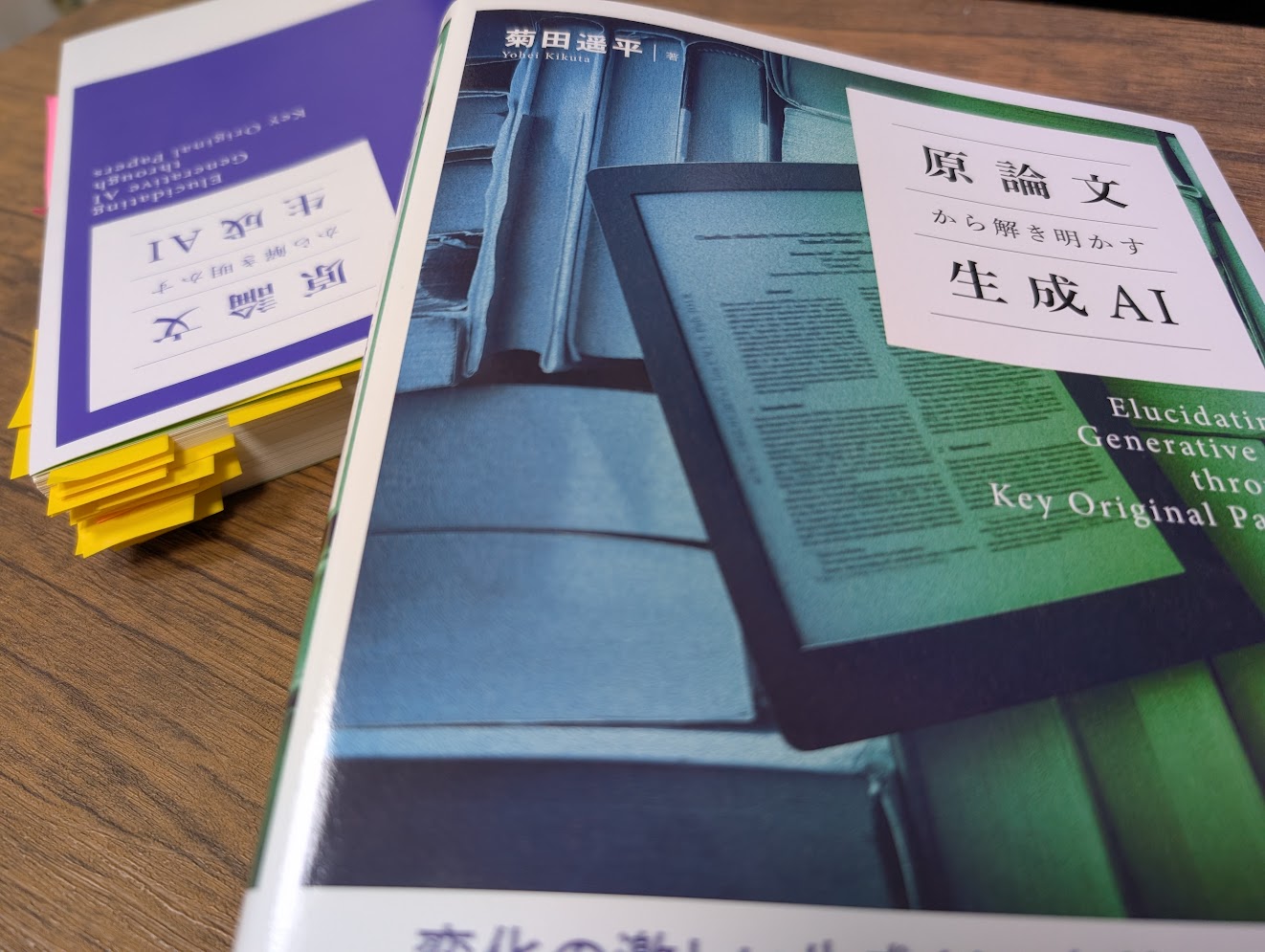
論文との付き合い方が心に響く
この書籍は原論文を読み解くことで生成AIの重要な理論的基礎を理解する本です。そのため、プログラムを作るとか、アプリケーションを作るという書籍とは異なります。
最初の章では論文を読む上での言語化しづらい&されづらい技術について、ひとつひとつ説得力のある形で丁寧に解説されています。これはまさに研究室で輪読などを通して少しづく経験値を積んで学んでいくような内容で、とても共感できる内容となっています。以下のような章立てとなっています。
- 1.2 論文を読み解く技術
- 1.2.1 論文を読む環境の構築
- 1.2.1.1 論文を入手する
- 1.2.1.2 論文を電子媒体で読む
- 1.2.1.3 論文は人間が書いたものであることを認識する
- 1.2.2 自分の力で論文を読み解くための技術
- 1.2.2.1 議論が成立する条件を確認する
- 1.2.2.2 具体例を構成する
- 1.2.2.3 実装を読み解いて理解を深める
- 1.2.2.4 重要となる参考文献は踏み込んで調べる
- 1.2.2.5 アウトプットすることで理解を深める
- 1.2.3 自分以外の力も借りて論文を読み解くための技術
- 1.2.3.1 少人数で深く議論する
- 1.2.3.2 論文の著者に直接質問する
- 1.2.3.3 ウェブ上で議論する
- 1.2.3.4 生成AIを使う
- 1.2.1 論文を読む環境の構築
そういった意味では、研究室に配属する前だけど研究に興味を持ち論文を読み始めた学部生が手に取ると良いのではないかと思います。もちろん、数学の基礎的な素養を持つ研究者やAIエンジニアが、基礎知識を補強するために読む本としてもオススメできます。
ユーモアのセンスが光る
技術書や専門書は往々にして読んでいて眠くなるものですが、ユーモアや個人的な面白い体験談をテキストに潜ませて飽きさせないような書もあります。この本はそういったユーモアのセンスが非常に良く、時に論文に対する解釈や現代から見た視点を交えつつ、飽きずに読み進めることができます。おもわずツイートをしてしまいました。
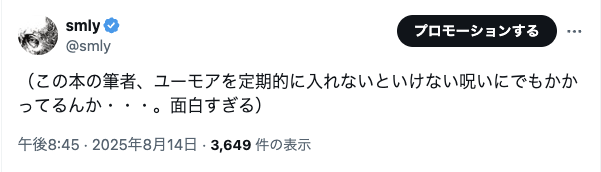
ネタバレを避けるために具体的な内容の紹介はしませんが、Attention 機構の入力例には笑いました。
理論的基礎の説明がよく整理されている
論文紹介は下手に全部を紹介するといくらでも内容が膨らむのですが、こちらの書籍では本質的なトピックを上手に取り上げつつ、必要に応じて背景となる技術について丁寧に紹介されています(ただし数学の基礎は習得済みとする)。3章の Transformer では論文における重要な主張である「並列可能性」を強調して RNN との違いを明らかにしつつ、新しい概念と既存の概念をそれぞれ整理して解説されています。この解説も論文を読み解く技術で紹介されているように「具体例を構成する」という形で紹介されているため、すんなりと理解できます。
あとがき
物理本をいただいたのですが、内容が良かったので電子版も買いました。Amazon から Kindle 版が購入できます。もっと紹介すべき&したいところが多々あるのだけれど、やらなくてはいけないタスクがあるので発売日深夜の滑り込み短め紹介です。ごめんなさい!そして素晴らしい本をいただきありがとうございました!

